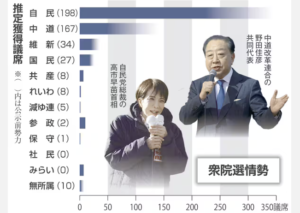加賀藩独特の被差別部落(以下、部落)の身分である「藤内」と医業の関係に注目し、小説を出版した故庄田望氏は、考察を深めるために地域での聞き取りを実施し、金沢部落史研究会の研究誌に報告していた。富山、石川両県では行政や地域社会が部落問題に背を向けてきたため、近現代の藤内につながる人々の様子を把握できる資料が非常に少ない。庄田氏の報告に注目してみよう。
加賀藩独特の被差別部落(以下、部落)の身分である「藤内」と医業の関係に注目し、小説を出版した故庄田望氏は、考察を深めるために地域での聞き取りを実施し、金沢部落史研究会の研究誌に報告していた。富山、石川両県では行政や地域社会が部落問題に背を向けてきたため、近現代の藤内につながる人々の様子を把握できる資料が非常に少ない。庄田氏の報告に注目してみよう。
庄田氏は小説執筆の動機を、1910(明治43)年生まれの母の「藤内医者」の思い出に、心ひかれたからとしている。このため出版した本には、小説とともに母の手記も掲載した。
母は大正時代初期、旧松任町(現、石川県白山市)で育った。村人は腰まで沈むような泥田もある中で農作業に従事しており、<便利だったのが、藤内の医者でした。(村はずれの掘っ立て小屋のような住まいに住み)頼めば走ってくる気軽な医者でした>としている。<和服でいつも大きなこうもり傘をもっていて、親切に病人に接していた>とも。村人とは昔から独特の関係があり、支払いは米ですることもあった。また村人は正月にくず米で団子を作り、藤内とされる人々がもらいにきたという。
庄田氏は、この医者の姿を求め、2000年ごろに旧松任町を中心に聞き取りをした。その中で、1923(大正12)年生まれの女性から「松任の開業医でない人に2、3回往診してもらったことがある」との証言を得た。信玄袋を提げてきて、最後にいろり端に置いた乳鉢で薬を調合した。近所では「やぶ医者」と陰で言い、受診をやめろという声もあったが、「(開業医にかかれるのは)裕福な家に限られ、(24軒の)自分の村では2、3軒しかなかった」と話している。ただ、この医者と藤内との関係を否定する人もいた。
富山、石川の部落問題に関心を持つ人の間では、前回紹介したように加賀藩下で例が多いことから、「藤内と医業」というテーマは注目されてきた。医業を差別される側が担ったことへの疑問符も人々を引きつける。富山、石川の部落史研究の第一人者だった故・田中喜男氏も「平常の交際では火や食を一緒にしないんですが、病気のときは藤内医者に肌を診てもらっているんですね」などと、江戸時代以前の差別の不思議について語っている。
全国的にも、被差別民と医業の関係に注目する研究がある。「近世の被差別民と医薬業・再考」の論考がある部落問題研究者の斎藤洋一氏(73)は、滋賀県にこの問題での詳しい研究があるという。部落解放同盟滋賀県連の丸本千悟書記長は「滋賀の部落では、近世に一定数の医者が存在し、活躍したのは事実です。以前の県の部落史でも取り上げています」と語る。
斎藤氏は、他にも全国で被差別民が医業と関係していた事例を多数、前記の論考で紹介している。さらに、世界規模での両者の関係にも注目し、「東アジア、インド、ヨーロッパでも、医者・薬屋が『賤民』とされることがありました。なぜそうなるかというと、血や死への忌避や『人間と動物のけがや病気を治す』力への畏怖(いふ)などが関係するのではないかと推測しています」という。
一方、いずれの場合も被差別民の医者とは別に、社会的ステータスが高い非賤民の医者・薬屋が存在した。斎藤氏は「両者を分け隔てるのは何かも考えなければなりません。それにしても、最大の謎は、人間と動物のけがや病気を治した人々が、なぜ差別されなければならなかったのか、ということになります」と指摘した。
https://mainichi.jp/articles/20231224/ddl/k16/040/101000c?inb=ra
引用元: ・【富山】被差別民も医業担う、加賀藩下で例が多く…「人間と動物のけがや病気を治した人々が、なぜ差別されなければならなかったのか」 [樽悶★]
感染症やらなにやらのリスクがあるので忌諱されたんだろ
差別問題を顕在化させて金儲けする集団
近世の被差別もとらえ直し必要なのでは。